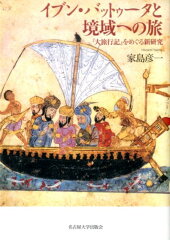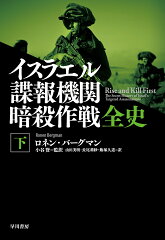本年1月10日から 「読書感想文もどき」に至らなかった「敗戦記」
というのをアップしていますが、今回12回目です。
イラストもあえて、同じものを使用、趣旨も同じで、硬軟とり交ぜ、
読者への何らかの参考となればと・・・
1.実存主義とは何か
増補新装版 J-P.サルトル/著
伊吹武彦/他訳
出版者 人文書院 1996.2
これも、敗戦記の典型です。
読んできて、字面は、追えます。また、サルトルが反論に応える
くだりで、引用するハイデッカーやルソーの、行動は、他で読ん
で知っています。
では、本書の理論を読み込み、理解・咀嚼できたかというと・・
気力が続かないんですね。
また、出口さんの引用で、お茶を濁します。
す。
もしも神が存在するとすれば、世界を創造し、世界の本質
や人間の本質を決定するのは神です。
しかし神が存在しないとすれば、人間の赤ちゃんは、まず
物体としてこの世に現れます。
そして成長するに従って、人間はさまざまなことを学び
人間の本質について、あれこれと考え始めます。
このようにして人間は、「自由な実存として存在している
」とサルトルは考えました。
(出口治明:哲学と宗教全史P435)
2.ウイルスの世紀
なぜ繰り返し出現するのか
山内一也/[著]
出版者 みすず書房 2020.8
20世紀後半以降、人間社会に次々と出現した新ウイルスを「エマージ
ングウイルス」という。
新型コロナウイルス(COVID-19)をはじめ、数々のエマージングウイル
ス事例を通じてウイルスと人間社会の関係を俯瞰しています。
著者は易しく書いているのであろうが、私の前提知識ではやはり難し
い。
末尾の「ウイルスとともに生きる」から少し引用。
野生動物と共存していくということは、彼らの保有するウイルスとも
共生する必要があるということを意味している。野生動物の生息域に
ヒトが入り込む機会が多い現代社会では、野生動物を自然宿主とする
さまざまなウイルスから、いかに感染を防ぐかがもとめられることに
なるだろう。新型コロナウイルスは、二十一世紀がウイルスとの共生
の道をさぐる時代に行ったことを、われわれに見せつけているのであ
る。 P232
3. グローバル経済の歴史
シリーズ名 有斐閣アルマ Basic
河崎信樹/著 村上衛/著 山本千映/著
出版者 有斐閣 2020.8
地球規模での交流や相互依存関係は、どのような世界から始まり、
いかに広がり深まってきたのか。
グローバル経済の総合的な歴史を学べる形となっています。
終章のグローバル化の行方から引用します。
グローバル化と新たな課題 3つ
1.プラットフォーム・ビジネスの問題
規制対象の巨大企業自体がグローバルに活動しているが
ゆえに、それに対する規制もグローバルにならざるを得
ない
2.地球環境にかかわる問題
3.感染症の問題
ビジネスや観光などを目的とした人の国際的な移動が活発化
先は読めない 4つの方向性のどれか?
・世界各国が協力して課題に取り組む
・1930年代に逆戻り
・グローバル化が適切な形で制御
・多くの課題を解決できないまま加速 P362-364
4. イブン・バットゥータと境域への旅
『大旅行記』をめぐる新研究
著者 家島彦一/著
出版者 名古屋大学出版会 2017.2
イブン・バットゥータの「大旅行記」を完訳した著者が、イブン・
バットゥータ研究の基礎知識を整理し、記録が伝える「海域」と
「陸域」の関連性や違いを分析しています。
私を含む、平均的な日本人にとって、この時代は「世界史の考察」
の弱い部分ですよね。教科書で昔習ったが、どうもヨーロッパ史や
中国史ほど全体が頭の中でリンクしにくい部分委思います。
14世紀の初めにモロッコで生を受けたイスラームの法官、イブン・
バットゥータは、なぜ30年に及ぶ大旅行を達成し得たのか。
その背景が、問題となります。
要因は、モンゴル世界帝国による平和(パクス・モンゴリカ)と
イスラーム世界の安定した権力(デリー・スルタン朝、エジプトの
マムルーク朝、マグリブのマリーン朝など)により、インド洋海域
世界とユーラシア大陸を相互に結ぶ国際的な交易ネットワークが、
1つの世界システムとして成立していたことが挙げられます。
原タイトル:Rise and kill first
ロネン・バーグマン/著
小谷賢/監訳 山田美明/訳 長尾莉紗/訳 飯塚久道/訳
出版者 早川書房 2020.6
成功、失敗、および倫理的代償について、その実情を描き出し
ています。
すさまじいモノです。
私は渦中にあるのでなく、単に一読者であり、身の危険を知らず、
気楽なものです。
今回読んだのは、下巻だけですが、十分堪能。。
以前、フレデリック・フォーサイスものを読んでいました。
を日本語訳で、読みました。
クションでしょうが。フォーサイス著作(これもノンフィクシ
ョン?)の読後感と、同じ疑問を感じました。
よく、調べているが、一般人に情報公開して問題ないのか?
著者(家族含む)は、身の危険をどう制御・回避しているのか?
時間が経過し「現在進行形のホット情報」でなく「歴史上の出来事」
だから問題なし、ということなのでしょうか。
最後に解説から引用
「我々日本人の感覚からしても、暗殺行為は到底受け入れられるよう
な話ではないか、国民の安全を確保するためにはここまでやらざるを
得ない国もあるということである。」P365